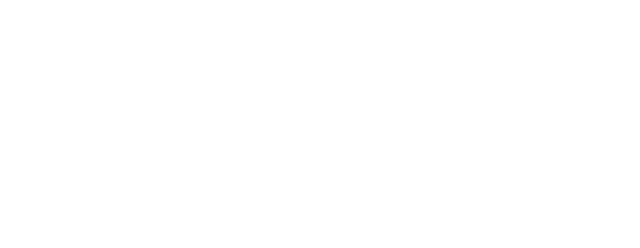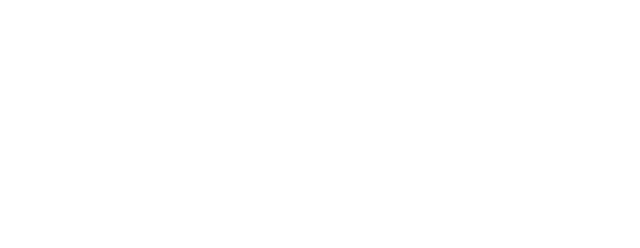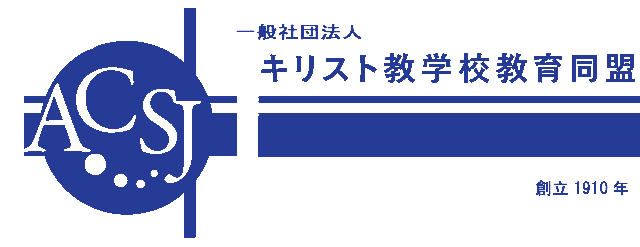キリスト教学校教育バックナンバー
特別講演
時代に立ち向かうキリスト者
河井道の教育理念
河井道の教育理念
大口 邦雄
河井道は一八七七年(明治十年)に伊勢山田市で生まれた。伊勢神宮の神官であった父親はその職を失い、河井道が九歳のとき北海道に渡った。父親は、サラ・C・スミスという長老派の伝道師が札幌に開設した女学校(後の北星女学校)に娘を入学させた。学校嫌いで内気だった「おみちさん」は、サラ・スミスの手によって開花した。スミスの教育は、一人一人の子供の内側から可能性を引き出してやることにあったと思われる。後に、河井道の学校は、この点で公立学校とは根本的に異なる理念の上に建てられることになった。園芸を教育に取り入れるという奇抜な発想も、このときの経験に基づいている。
ここで新渡戸稲造の教えを受けた河井道は、一九〇〇年、彼の勧めでフィラデルフィアのブリンマー女子大学に入学した。その教育は、キリスト教精神に根ざし、全寮制のもとで行われるリベラル・アーツの教育であった。ルームメイトとの親しい交わりを経験した河井道の「国際性」は、人種を超えた人と人との人格的信頼関係に基礎を置いている。また、強い平和志向が信仰と一体となっているのは、クエーカー教徒との交わりを深めたためであろう。リベラル・アーツの教育は、個人の人格と知性の発展そのものを目指す教育であって、その結果社会における優れた指導者としての資質を身につけるに至る。河井道が、優れた女性指導者に育ったのは、その成果と言えよう。
一九〇四年大学を卒業して帰国した河井道は、一九一二年、日本YWCA同盟の最初の日本人総幹事に就任し、日本代表として幾度かアメリカ、ヨーロッパに赴いた。近代化は必然的に、国際世界への関与をもたらす。そのとき、それを内側から支えるものが何であらねばならないかを河井道は独特の鋭い感性で感じとったのであろう。そして、それまでの日本人には無かった、新しい、自由で、解放された近代的女性像を思い描いたと思われる。第一次世界大戦後の一九二一年、ジュネーヴで、ドイツとフランスの若い女性が、最初は戸惑いながらも、駆け寄って手を取り合い、互いの目を見つめあう様子に深く打たれる。男の世界は所詮、国家と政治の世界である。そこでは正義と正義がぶつかりあって、近代化が進めば進むほど、より大規模で残酷な戦争をもたらす。欧米の心ある女性達の心を曇らせたこの課題を、河井道は共有することのできた国際人であった。「戦争は、婦人が世界情勢に関心を持つまでは決してやまないであろう。婦人の上にこそ、世界平和を恒久的なものにするため努力しつづけ計画しつづけ祈りつづけ犠牲をさえも払いつづける責任が、課せられている」と確信した。「わたしたちの希望は数十年の間には実現しないかも知れない。しかし、その責任の重荷は日本も含めてすべての国々の婦人によって分担されなければならない」と考える。ゆく手もさだかでない曲がりくねった道を、ただ一すじの光のみに導かれて進もうと決意し、自ら選びとった新しい歩みは「キリストの子供たちの先に立って暗い狭い道を照らしてゆく提灯持ち」であった。河井道は、YWCA総幹事のポストを擲って、まだ幼い少女達を育てるという、迂遠な道を選んだのである。実践的な宗教教育のほか、当時としては珍しく、国際や園芸の授業をカリキュラムに取り入れたいと考え、アメリカ、ヨーロッパに視察の旅にでる。中でも、英国のスワンレー女子園芸大学を訪れて園芸の源流に辿り着き、これが日本に園芸をもたらす発端になるのである。
世界大恐慌が始まる直前のこの時期、新渡戸稲造をはじめ友人達は、学校の設立に一様に反対した。それにも関わらず、教え子たちの「小さき弟子たちの群」や、創立の意図に賛同する友人、知人の支援を得、あらゆる困難を克服して一九二九年三月遂に文部省の許可を得た。河井道五十二歳のときである。生命の源から沸きあがる恵みの泉である女子の学びの園を恵泉女学園と名付けた。
しかし平和への願いも空しく日本は戦争に突入する。当時の恵泉誌の巻頭言を読むと、河井道は戦争指導者たちの言辞を肯定していたかのように見える。しかし、そのすぐ後に、その言葉の真の意味が何でなければならないかについて語る。それは今日におけるわれわれの考えと基本的に矛盾しない。つまり、河井道は、時代を超えて正しいことは、そのまま受け入れた。しかし、受け入れるわけに行かないことには、断然拒否したのである。河井道が戦争と言う厳しい試練を毅然として乗り超えたのは、実に復活の信仰であった。一九三九年に著した自伝的書物『私のランターン』の最後でこう述べる。
「この世には幾日かの間、人には何事もなし遂げられていないかのように見える日々があるし、わたしたちクリスチャンは十字架にかけられ、死んで葬られたと考えられがちである。しかし、わたしたちには第三日目が与えられていると、わたしたちは信じる。」
一九四五年八月、戦争の終結とともに、その第三日目が来た。河井道はすでに六十八歳だったが、戦後、教育刷新委員会の委員となり、教育基本法の起草に関わり、また、短期大学制度の導入を強く主張した。一九五三年二月、河井道はその生涯を閉じた。
河井道のアメリカのクラスメートを魅了したらしい『私のランターン』の冒頭の章「彼岸桜」は、河井道のいかにも日本人らしい美的、あるいは倫理的感性を感じさせる。一つには、古典的教養を持つ父親の教育を受けたこともあろうが、しかし、それだけではない。実は「欧化主義」の時代は、わが国における「文芸復興」の時代であり、政府の意図した「教育勅語」とは別の場所で、新しく、個人の自覚、民族の自覚が起こって来た時代でもあった。河井道が郷愁をもって描く古く懐かしい日本は、こういった文学的動向と無関係ではあるまい。河井道が外国の人々から重んじられた理由は、河井道が内面的に日本人としてのアイデンティティーをしっかりと持つ、しかし異文化にも開かれた心を持つ日本人だったからなのである。河井道が、外国のミッションボードの援助に頼らず、自らの手で新しい学校を創立しようと志した理由の一つも恐らくここにある。
河井道とほとんど同時代を生きた女流文学者片山廣子が、大正五年に公刊した歌集『翡翠』には、日本的な感性がヨーロッパ近代の感性と出会って、新しい文学的感覚を和歌の世界にもたらしたように感じられる歌がある。他方、廣子自身が「覚めんとして覚め得ざる心の姿、真面目なる女の内的生活の記録の一片」と語っている一群の歌は、鬱屈した思いを率直に陳べたもので、そういった心境を和歌に詠むことは、勇気を要する「新しい路への一歩」だったのだろう。河井道は、片山廣子のような当時第一級の教養ある婦人が、内面の秘められた世界でしかできなかった女性の心の解放を、教育の世界で現実のものとした先駆者のひとりになった。そういう意味で、河井道という人が、新しい一人の女性として成長していった出来事は、東と西の出会いであったと言えるであろう。
河井道は、つねに聖書に照らしつつ自らの経験をふり返り、そこに基礎を置きつつ独自の思想を築いて行く実践家であった。あの戦争のさなかにあって、毅然として時代に立ち向かった強さの秘訣がそこにある。河井道の打ち立てた教育理念は、その本質的重要性を今も失ってはいない。しかし、河井道は教育理念そのものを、詞として残さなかった。第四代の学園長秋田稔以来、「恵泉のこころ」を次のように表現している。
1.神以外の何ものも恐れない独立人として目覚めるとともに、隠れたところで名を没して友なき人の友となる。
2.世界に向かって開かれた心を持つ、国際的にも信頼される人間になる。
3.自然を愛し、土に深く根を下ろした着実な人間らしさを持った、労を惜しまぬ人間になる。
こころの学校恵泉は、とかく偏差値の片寄りがちな風潮の中でいまだに時代に立ち向かっているとも言えるであろう。河井道の本質は、われわれを取り巻く諸問題につねに眼を向け、たとえそれが迂遠なしかたであろうとも、真っ向から立ち向かい、開拓してゆこうとする精神的態度そのものにある。われわれの前には、未来を大きく変えねばならない大きな問題が幾つかある。近代化を内側から支え得る女性の創造、少子化の克服、生涯教育の必要性、正しい家庭環境、平和憲法下における真の日本人を育て、美しい国土に変貌させる課題等々である。それらが、いかに曲がりくねった困難な道であっても、ただ一筋の光に導かれて進むのが、河井道の精神を継ぐ、今日的課題なのである。
〈恵泉女学園学園長・大学長〉
キリスト教学校教育 2005年7月号4面