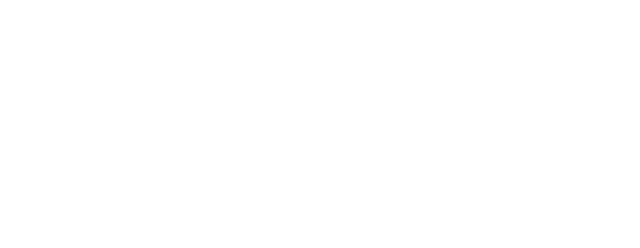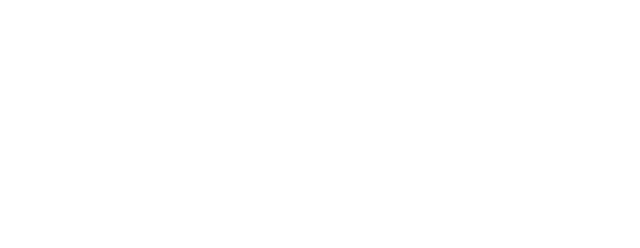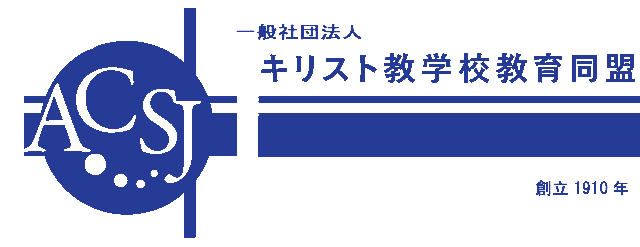キリスト教学校教育バックナンバー
第四十六回小学校代表者研修会
主題「共に重荷を担う-生命をめぐる新しい時代の倫理観」
講演 「いのちの尊厳」をめぐって -科学技術者としての医療との関係で考える-
関 正勝
「共に重荷を担う」という主題が与えられていますが、この主題設定のうちにキリスト教に基づく教育を謳い、初等教育に取り組んでおられる先生方の置かれた状況の厳しさと困難さがよく表れている、と思っています。
生命倫理の必要
科学技術としての医療の発達は、革命的でもあり、わたしたちの誕生・生・死の過程への介入の度合はますます拡大されてきています。そのことのメリットと共にデメリットも多く出てきています。デメリットの多くは医療は、科学技術としての性格から、その科学の人間的、あるいは倫理的価値と意味を問わず、可能だから実行するという態度に基因しているといえましょう。意味や価値を問うことを止めることで、科学技術は身軽になって目的というか、結果を求めて驀進してしまう。そこに科学技術と人間的意味の間に大きな乖離が生じてしまっています。生命倫理が登場し、その必要が訴えられるのは、意味を問う存在としての人間の権利のためである、といえましょう。
したがって生命倫理は、基本的には科学技術としての医療に問いを投げ掛ける営みである、と考えられます。
生産性と社会性
今日のわたしたちの価値観を支配しているものは、端的にいえば〈生産性と社会性〉である、といえます。そのような価値観を根底から支えているのが科学技術でありましょう。実際、科学技術は、わたしたちの日常生活を便利に、快適に、衛生的で効率的に整えられたものにしてくれます。その事実の前で、そのように整えられた生活に背反するもの、例えば、病気、障がい、老い、そして死等々は隠蔽され、排除され、無いものとされてしまいます。そのようにして生産性と社会性がわたしたちの生活に対して求められてきます。そして、そのような存在から遠い存在は、不在化されかねない、少なくとも生き苦しいという状況を産み出すことになっています。
このような、人間の有限性がつきつける病気や障がい、老いそして死といった現実から一見、遠ざけてくれるように思える科学技術は、わたしたちを身体的経験から超越させて軽率の文明をもたらしています。時間的過程よりも結果だけが重視される世界を現実としています。現代医療は、脳死をもって死と見なし、ドナー・カードを所持していれば臓器提供者として扱います。脳死は人間の死だ、とする考え方は、現代文明の、脳に人格の在所を認める脳中心社会の特徴をよく表現しています。人間の人間たる理由は、〈考える〉ところにある、という主張です。このような考え方が、偏差値による子どもたちの存在の序列化を当然とする社会〈生産性・社会性〉をもたらしている、といえましょう。
しかし、今日、大切にされなければならないのは、情緒(センチメント)とか、身体経験といったものではないか、と思います。
関係としての知―身体知
身体経験がもたらしてくれる知は、関係が生み出すものでありましょう。出会いという経験、それは他者との関係、またその関係がもたらしてくれる自己自身との関係などによって成り立っている、と思います。真実の出会いは、受容されている自己の経験です。信ずることは、すなわち自分自身でも受け容れ難い現実のある自分が、神によって受容されていることを受け容れることだ、といわれます。わたしたちの身体は、自分には自由に出来ない、操作対象とし得ない現実があることをつきつけます。しかし、わたしたちは出会いによってそのような自分の身体的現実を受け容れることが起こります。
このような身体的現実があるにも拘らず、というのではなく、出会いの経験はこのような身体的現実があったからこそ今の自分がある、といえるような経験です。そのことは病い、障がい、老い、そして(他者の)死の経験に対してもいえるでしょう。
〈身体知〉は、関係知といえるように、理性がもたらす知が、分離や分析、対象化によって成り立っているのとは対照的に出会いによってもたらされる、といえます。その知と経験は、わたしたちのうちには、わたしがわたしと成長して行くために、抑圧されたり、排除されたり、切り捨てられたりしなければならない存在は何一つ無く、すべてはわたしが自らの新しい生命に出会うのに不可欠な存在であることを知らせてくれるでしょう。
存在と価値は不可欠
現代は、存在を特定の価値によって輪切りにし、序列化しますが、それは存在と価値を分離するからに他なりません。しかし、聖書は、神がわたしたちを創造して下さって、裸を〈恥ずかしがる〉必要のない存在とされ、而もそのことをもって〈極めて良かった〉、と語っています。裸であることを恥ずかしいと思う必要がない、ということ、それは自らの弱さや、無力さといった現実から自由であったことを意味しているでしょう。そのような現実が、差別や死にあたいする事柄ではない、と聖書は力を込めて語っています。そのためには、神以外のものを神としない決断が求められています。神以外のものを神としない、あの十戒の第一戒が選び取られているところでは、存在と価値の分離は起こらない、と迫られています。
この存在と価値を分離しない生き方には無限の情熱、コンパッションが求められているでしょう。
「わたしはある。」(出エジプト3・14)と語る神は、エジプトの奴隷となっている民の「苦しみをつぶさに見、叫びの声を聞き、その痛みを知」る神として、共感・共苦する〈熱情〉の神です。その神は、この世界にイエス・キリストを誕生させて下さいました。神のコンパッションが、存在と価値の分離する世界で戦っている。わたしたちの営みのすべては、この神のコンパッションへの応答に他ならないでしょう。
今、わたしたちに求められるのは、身体経験と、共感・共苦する能力をもって、〈希望に抗う希望〉(ローマ4・18)を生きることではないか、と思います。
〈聖公会神学院校長、前・立教大学教授〉
キリスト教学校教育 2004年4月号2面